資料作成の最初の一手は、主題(テーマ)を明確にすることです。結論を冒頭に示すことで、読む側は「この資料を読む価値があるか」を瞬時に判断できます。特にオンラインでは、ユーザーの多くがページをスキャンするだけで、平均的にはテキストの20〜28%しか読まれないという調査結果があります(Nielsen Norman Group, 2020)。つまり、冒頭で主題を示さなければ、せっかく作った資料も読まれない可能性が高いのです。
主題(テーマ)を確認することの重要性
資料の主題は、作り手の「言いたいこと」ではなく、受け手の関心や組織の課題に基づいて設定する必要があります。時間はビジネスにおける最も限られた資源です。受け手が興味を持たない資料は、いくら詳細であっても無駄になりかねません。
主題を決める際には、以下のチェックリストが役立ちます:
- 誰が受け手か?(意思決定者/実行者)
- 受け手が抱える課題は何か?(一文で整理)
- この資料で期待するアクションは何か?(決裁・承認・情報共有など)
- 成否はどのように測るか?(KPIや数値指標で明示)
こうした視点で主題を設定することで、資料の説得力と実務的価値が格段に高まります。
主題を最後まで押さえ続ける
資料作成中に最も陥りやすい失敗は、途中で主題が曖昧になることです。たとえば会議中に話が脱線して、もとのテーマに戻らないまま終了してしまうことはよくあります。資料作成も同じで、主題がぶれると、結論が見えない、まとまりのない資料になってしまいます。
主題を最後まで意識するための方法:
- 最初に「主題と目的」を1文で書く
- 目次や見出しを作り、各章で主題に沿った内容だけを記述する
- 資料の最後に「主題の再提示」と「期待するアクション」を示す
この手順を踏むだけでも、資料の明確さと説得力は大きく向上します。
イシューからはじめる
ビジネス資料作成のプロセスでよく用いられるのが、「イシュー(issue)」の特定です。MBAグロービス経営大学院によると、イシューとは「論理を構造化する際に、何を考え、論じるべきか」を示す概念です(グロービス, 2025)。
つまり、イシューを特定することで、資料作成の目的や受け手の関心に沿った議論が可能になります。無駄な分析や情報収集を避けることができ、資料の効率と質を高められます。
主題(テーマ)を相手と共有する
主題が決まったら、それをチームや受け手と共有することが重要です。共有されなければ、資料はただの情報の集まりに過ぎず、人を動かす力を持ちません。
論理を構造化する際に、その場で「何を考え、論じるべきか」を指す。 「イシューを特定する」とは、「何を考えるべきか」「受け手の関心は何か」を熟考し「考え、論じる目的」を押さえることを指す。
(MBAグロービス経営大学院)
具体的な方法の例:
- 1枚サマリー
- タイトル(主題を一行で)
- 目的(何を決めたいか)
- 結論(推奨アクション)
- 主な根拠(箇条書き3点)
- 次のアクション(誰がいつ何をするか)
- 会議アジェンダ
- 目的(1文で)
- 主題(決定すべき論点)
- 論点別所要時間・担当者
- 期待する決定(Yes/No/次回検討事項)
こうしたテンプレを用いれば、主題が常に共有され、資料作成や意思決定の効率が飛躍的に向上します(Harvard Business Review, 2021)。
事例:JFKの月面着陸演説
主題共有の重要性を示す歴史的事例として、1961年5月25日のジョン・F・ケネディ大統領の議会演説が挙げられます。ケネディは「今後10年以内に人間を月に着陸させ、安全に地球に帰還させる」という明確な主題を掲げました。この明確さが国民の行動を一致させ、史上初の有人月面着陸へとつながったのです。
まとめ:主題を最後まで押さえる3つの習慣
- 冒頭で結論を示す
- チェックリストで主題に沿った内容を確認
- 資料・会議で主題を共有し、脱線を防ぐ
主題を意識して資料を作るだけで、受け手の理解と行動を促す力が格段に高まります。日常の資料作成でも、ぜひこの手順を実践してみてください。
MSDコンサルティング
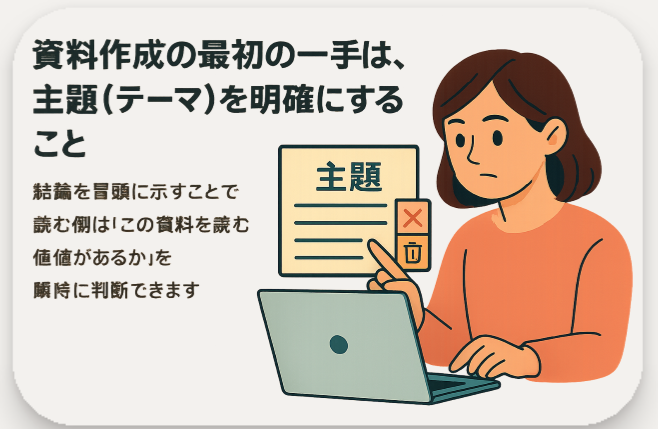
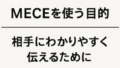

コメント