合理的に予見可能な誤使用とは
合理的に予見可能な誤使用( reasonably foreseeable misuse)とは、EN ISO 12100: 2010(JIS B 9700: 2013)の定義では「設計者が意図していない使用方法であるが、容易に予測できる人間の挙動から生じる機械の使用」です。リスクアセスメントを行う時には、必ず「合理的に予見可能な誤使用」を考慮しなければならないとされています。
設計者が「そんな使い方はしないだろう」と考えても、実際の現場では人間の反射的行動や知識不足、不注意により“誤った使い方”が必ず起こり得るのです。
なぜ考慮する必要があるのか?
なぜ、リスクアセスメントで、合理的に予見可能な誤使用を考慮しなければならないのか? その理由は、事故や労働災害の9割以上が、この合理的に予見可能な誤使用が原因になっているからです。合理的に予見可能な誤使用を考慮して、間違った使い方をしても怪我をしないことを考えなければ、真に機械の安全性を高めることができないからです。
合理的に予見可能な誤使用を考慮する理由は、単に事故を防ぐためだけではありません。
- 現実の人間行動に即した安全設計を行うため
- 教育やマニュアルでは防ぎきれないミスを機械側でカバーするため
- 責任所在の明確化(製造物責任法・労働安全衛生法対応)のため
もし誤使用を想定せずに設計した場合、事故発生時に「設計上の安全配慮義務違反」と判断されるリスクもあります。特に欧州では、CEマーキングの適合性評価でも「合理的に予見可能な誤使用」を設計段階で検討したかどうかが重要視されます。
どの段階で考慮するのか?
リスクアセスメントにおいては、以下の3つのステージで誤使用の考慮が必須です。
- リスクアセスメント開始時
- 機械の性能、特徴、使用者、使用環境を特定する際に、人間の誤った行動パターンも想定する。
- リスク低減方策を検討する時
- 安全防護(ガード、インターロック)、付加保護方策(フェールセーフ、非常停止装置)を設計に反映。
- 使用上の情報を決める時
- 取扱説明書、教育訓練内容、警告ラベルで「誤使用を完全に防げない部分」を補う。
考慮すべき人間の5つの典型的な誤使用行動
厚生労働省のガイドライン(基安安発第0731004号)では、次の5つが代表例として示されています。
故障時の反射的行動
事故やトラブルに直面すると、人は咄嗟の判断で危険な行動をとりがちです。
例:クレーンの吊り荷が揺れた際に、思わず手で押さえに行き指を挟む。
集中力の欠如・不注意行動
疲労や単調作業により、判断力や注意力が低下してミスが発生します。
例:自動車運転でのブレーキ・アクセルの踏み間違え、医療現場でのボンベ取り違え。
作業中の省略行動
「面倒だから」と正規手順を飛ばす“近道行動”。
例:保護カバーを取り付けないまま機械を再稼働。横断歩道を使わず車道を横切る。
機械を止めずに使い続ける行動
生産性を優先し、安全より稼働を優先する。
例:運転中の機械に給油作業を行う、新幹線の異音を無視して運行を継続する。
正しい手順を知らない行動
教育不足や知識欠如により、誤った使い方をしてしまう。
例:新人作業者が操作マニュアルを理解せずに危険操作を行う。
まとめ:誤使用を前提とした設計が安全をつくる
「合理的に予見可能な誤使用」は、設計者にとって“責任回避のためのチェックリスト”ではなく、現場で必ず起こり得る人間行動を織り込んだ設計思考です。
- 誤使用を完全に排除することは不可能
- だからこそ「誤使用があっても大事故につながらない設計」が求められる
安全設計の本質は、人間の弱さを受け入れ、それを補う仕組みを作ることにあります。

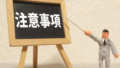

コメント