はじめに
電気は私たちの生活や産業活動に欠かせないエネルギーですが、誤って人体に流れた場合には深刻な危険をもたらします。感電による人体への影響は、電流の大きさ(アンペア)、電流の通過時間、体内を流れる経路、そして人体の電気抵抗によって決まります。場合によっては「軽い痛み」から「火傷」、「呼吸困難」、「心室細動(致命的な不整脈)」、さらには「死亡」に至ることもあります。
技術者にとって重要なのは、電流の数値と人体への影響を正しく理解し、設計・保守・作業の場面で「この条件なら人体にどの程度危険なのか」を瞬時に判断できることです。
感電の重症度を決める要因
感電事故のリスクは、単純に「電圧が高いから危険」とは言えません。以下の要因が組み合わさって結果が決まります。
- 電流の強さ(mA 単位)
数mAでも人体に影響を与えます。致死に至るのは100mA前後から。 - 電流の種類
交流(AC)は心臓に影響を与えやすく、特に周波数50/60Hzは人体に危険。直流(DC)は連続的な収縮や熱的損傷を起こしやすい。 - 通電経路
指先から腕、胸部を経由して心臓に至る経路が最も危険。逆に足先だけの通電は比較的リスクが低いが、やけどや転倒を招くこともある。 - 通電時間
0.1秒以内なら致死リスクは低いが、1秒以上になると急激に危険性が高まる。 - 人体の電気抵抗
乾燥した皮膚で約2,000Ω、濡れた皮膚や傷口を介すると数百Ωまで下がる。抵抗が低いほど同じ電圧で流れる電流は大きくなる。
電流値と人体への影響(IEC/日本産業衛生学会資料に基づく)
| 電流値 | 主な影響 | 技術者向けの注意点 |
|---|---|---|
| 0.5~1mA | かすかな痛み・しびれ。危険性はほぼなし。 | 静電気のショックと似たレベル。ただし不意打ちによる転倒事故に注意。 |
| 5mA | 明確な痛み。 人体に悪影響を及ぼさない最大許容電流(AC)。 | 5mA程度を基準に設計されることが多い。人体保護を考慮した回路設計に重要。 |
| 10~20mA | 「離脱不能電流」。 電線を握った手が勝手に離せなくなる。 筋肉痙攣・呼吸困難・血圧上昇。 | この領域に入ると自力で脱出できない。保護装置の作動が唯一の救命手段。 |
| 50mA | 強いショック。気絶や臓器損傷の可能性。 心臓の不整脈(心房細動)が発生しうる。 | 医療機器や実験設備では特に注意。1秒以上の通電は極めて危険。 |
| 100mA 以上 | 心室細動が発生。 心肺停止 → 数分以内に致死。 | 100mAは「致死電流」と呼ばれる。交流100V/200Vでの事故はこの領域に入りやすい。 |
具体例:200V活線に接触した場合
人体抵抗を 2,000Ω と仮定すると、オームの法則より I=200V2000Ω=100mAI = \frac{200V}{2000Ω} = 100mAI=2000Ω200V=100mA
となります。100mAは心室細動が起こる危険な値であり、200V活線への直接接触は即致死リスクを意味します。さらに皮膚が湿っていたり傷口があれば、抵抗はもっと低くなり、流れる電流はより大きくなります。
感電防止の仕組み:漏電遮断器(RCD/ELCB)
- 日本の低圧配電盤では、30mA・0.1秒以内で動作する高感度漏電遮断器が標準。
- 30mAは「心室細動に至る前の値」として設定されているが、作動するまでに瞬間的に数十mAが人体を流れるため、無傷では済まない可能性が高い。
- よって、漏電遮断器は「致死リスクを減らす装置」であり、「感電自体をゼロにする装置」ではない。
技術者が知っておくべきポイント
- 100Vでも十分に致命的であることを認識する。
- 作業時は電源遮断・検電・短絡接地を徹底する。
- 湿度や汗が人体抵抗を大幅に下げる → 夏場の作業は危険度が上がる。
- 保護具(絶縁手袋・絶縁靴)は最後の砦。必ず規格適合品を使用。
- 教育と訓練:新入社員や非電気系の作業者にも感電の危険性を理解させることが重要。
まとめ
電流が人体に及ぼす影響は、わずか数mAから始まり、100mAに達すると心室細動により死に至ります。特に交流100Vや200Vといった日常的に使用する電圧でも十分に致命的であるため、「低圧=安全」という誤解は禁物です。
漏電遮断器や絶縁保護はあくまで補助的な安全策であり、最も重要なのは「電源を切る」「通電状態で触れない」という基本動作です。技術者はこの数値と原理を理解したうえで、日々の業務に臨む必要があります。
MSDコンサルティング


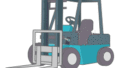
コメント